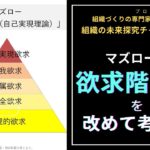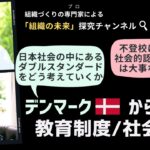Vol.122 外部から専門家として組織を支援するときによくあるお悩み
今回は外部コンサルタントとして、企業組織を支援する仕事をもっと増やしていきたい方のご相談にお答えします。「組織や人事領域の支援をしたいけど、なかなかそのニーズを持った経営者に出会えない」「これまで社会保険労務士としての仕事しかしておらず、組織領域もやったことがない領域なので引き受けていいのか悩んでいる」「研修講師をしていて、もっと幅を広げてみたいがいつもお願いされる領域を超えた提案ができない」など、外部から企業組織を支援する立場でよくあるお悩みや、外部の専門家として組織開発に携わるときに忘れてはいけない観点などを解説します。